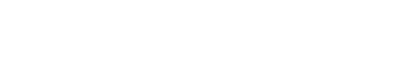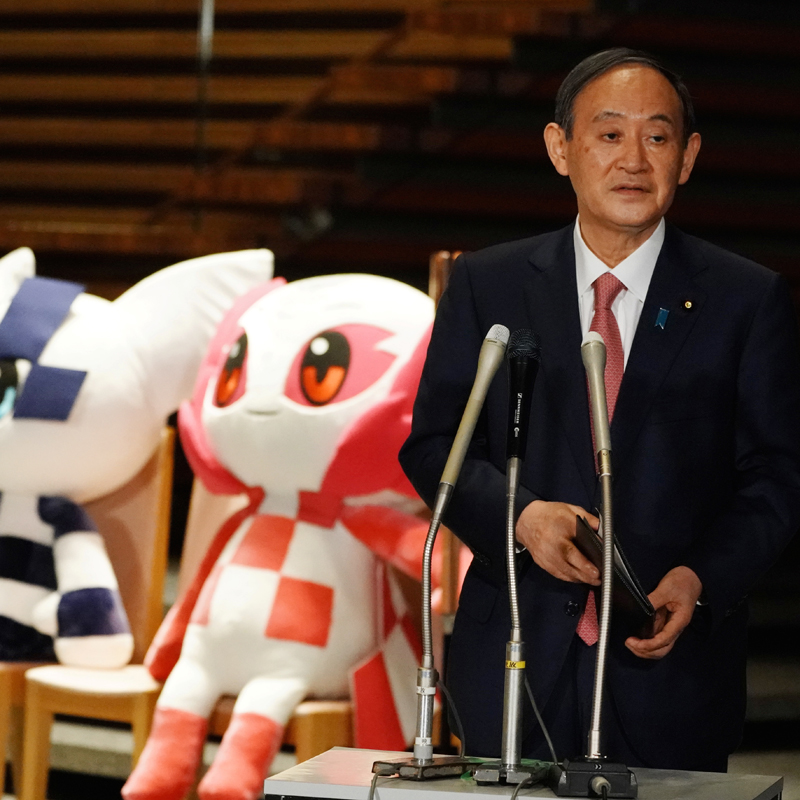なぜ政治家は顔で判断されるべきなのか?【中野剛志×適菜収】
「小林秀雄とは何か」中野剛志×適菜収 対談第2回
「なぜいま小林秀雄を読むべきなのか?」 新刊『小林秀雄の政治学』(文春新書)を上梓した評論家・中野剛志氏は次のように語っている。「未知の事態にどのように対応すればいいのか」を考えるとき、小林はまるで切籠細工のようにあらゆる方面から対象を照らそうとした。それは新型コロナにどう向き合うかについての「考えるヒント」にもなるだろう。『小林秀雄の警告 近代はなぜ暴走するのか』(講談社+α新書)の著書もあり、「イデオロギーの暴力」「言葉の怖さ」について問題意識を共有する作家・適菜収氏と語りあう。対談第2回。

■小林秀雄の言葉の裏表に政治学と文学があった
中野:現実を見たとき、切籠細工のように言葉を尽くす手間を省いて、ラベルを貼ると分かった気になる。これこそが小林秀雄が言ってる「意匠」ってやつですね。「様々なる意匠」って、あれ「様々なるイデオロギー」っていうことなんですよ。どうしてイデオロギーっていうものに人間は左右されやすいのか、また左右されるとどうして人間性を失うのか。それは全部言葉の難しさに起因しているんですね。このことを小林は繰り返し語っている。イデオロギーは、平板な言葉で人間を集団的に支配する。集団を支配するイデオロギーを論じるいうことは、それは政治学です。
小林秀雄の言葉の裏表に、政治学と文学があった。小林の文学論の裏面にある政治学、これがずっと見落とされてたと思うんです。
実際、彼自身が「社会科学者であるはずのマルクスと、文学者であるドストエフスキーが、結局同じことを言ってる」、「アプローチは違うけどふたりは同じことを言ってるんだ」というようなことを言っている。小林は世間では文学者ってことになってますけれども、じつはその裏側に政治学がある。そのことが見落とされてきたと思うんです。そして政治学というものは、丸山眞男みたいな知識人に代表されていたという感じがするんですね。
適菜:ラベルの問題は私が「B層シリーズ」で一貫して述べてきたことです。たとえばスーパーマーケットの刺身に「産地直送」「新鮮」というラベルが貼ってあれば、新鮮だと思ってしまう。魚をよく見ないわけです。ベルグソンは『笑い』で「ほとんどの場合、事物の上に貼り付けられたラベルを見ているだけである。そうした傾向は必要から生ずるのだが、しかし言語の影響がそれに拍車をかける」と述べています。語は事物のきわめて一般的な機能とごくありふれた側面しか記さず、事物とわたしたちとのあいだに割って入り、その語自体を生み出した必要の後ろにまだ隠されていない事物の形をさえ、わたしたちの眼から覆い隠してしまうと。
小林が言っていることも同じです。イデオロギーで判断するのではなくて、現象の具体性を見ろということです。この対談の第一回で「リバティー」と「フリーダム」の話が出ましたが、現実に即していない抽象的概念、イデオロギーは暴走します。ハンナ・アーレントは、エドマンド・バークがフランス革命の人権宣言を否定したのは正しかったと言っていますね。人間の普遍的な権利なんて無意味な抽象だと。
人類は二度の大戦、ナチスの蛮行を経験してきた。そして、イギリス人の権利とかドイツ人の権利とか個別具体的な権利しか残らなかったことを知ったと。権利とは継承された遺産であり、国民の権利という形でしか成り立たないと。

中野:はい。小林秀雄とハンナ・アーレントには共通点がある。何が共通点かというとアーレントは、「一回きり」「その人にしかない」「その一瞬にしかない」といったことを重視していましたね。小林もそのことをずっと言ってる。アーレントは集団が群れて動く大衆社会が嫌いでした。彼女が特に嫌ってたのが統計学ですね。社会科学上の統計学というのが成り立ち得るのは、人間一人一人が固有の存在じゃなくて横並びで同じ方向に行くというような大衆現象があるからだとアーレントは言うのです。要するに、集団主義的な大衆社会論、もっとはっきり言うと全体主義みたいな話と、統計学的な分析手法というものは、非常に親和性が高いというのです。そう言えば、アーレントだ何だと哲学者ぶって大衆社会批判や全体主義批判をしながら、統計学的な手法を振り回している変な学者がいますが、おそらく彼は何も分かっていないのでしょう。もっとも、その人は、その統計ですらインチキして大衆を煽動しようとしているから、論外ですけれどね。
適菜:今の日本自体が、統計学とプロパガンダで動くようになってしまいましたね。「近代科学の本質は計量を目指すが、精神の本質は計量を許さぬところにある」。小林はベルグソンについて、「彼の思想の根幹は、哲学界からはみ出して広く一般の人心を動かした所のものにある、即ち、平たく言えば、科学思想によって危機に瀕した人格の尊厳を哲学的に救助したというところにあるのであります。人間の内面性の擁護、観察によって外部に捕えた真理を、内観によって、生きる緊張の裡に奪回するという処にあった」(「表現について」)と言っていますが、小林の仕事もまさにこれです。
中野:そういう政治状況の問題を小林秀雄が戦後しきりと『考えるヒント』などで書いている。小林が『考えるヒント』で、ヒトラーの『我が闘争』を読み直してみたり、あるいは、プラトンだとか、『プルターク英雄伝』だとか、ペリクレスだとか、しきりに古代ギリシャの政治学の古典とか歴史に戻ったりする時期があるのですね。それが、安保闘争の頃と一致してるんですよ。だから、小林は政治に関心はあっただろうし、実際、政治について深く考察しているんですよ。
適菜さんの『小林秀雄の警告 近代はなぜ暴走したのか?』でも強調されてましたけど、小林は『大衆の反逆』を書いたオルテガ・イ・ガゼットに匹敵するような大衆社会論をやってますよね。
適菜:そうです。小林は「ヒットラーと悪魔」の中で、「人間は侮蔑されたら怒るものだ、などと考えているのは浅薄な心理学に過ぎぬ。その点、個人の心理も群集の心理も変わりはしない。本当を言えば、大衆は侮蔑されたがっている。支配されたがっている」と喝破しました。全体主義は一枚岩のイデオロギーではなく、そこには構造がない。煽動する側と煽動される側が一体となり拡大していく大衆運動です。ヒトラーは人性の根本は獣性にあると考えました。ヒトラーはその確信のもとに、大衆の広大な無意識界を捕えて、感情に火をつけたと小林は指摘していますね。